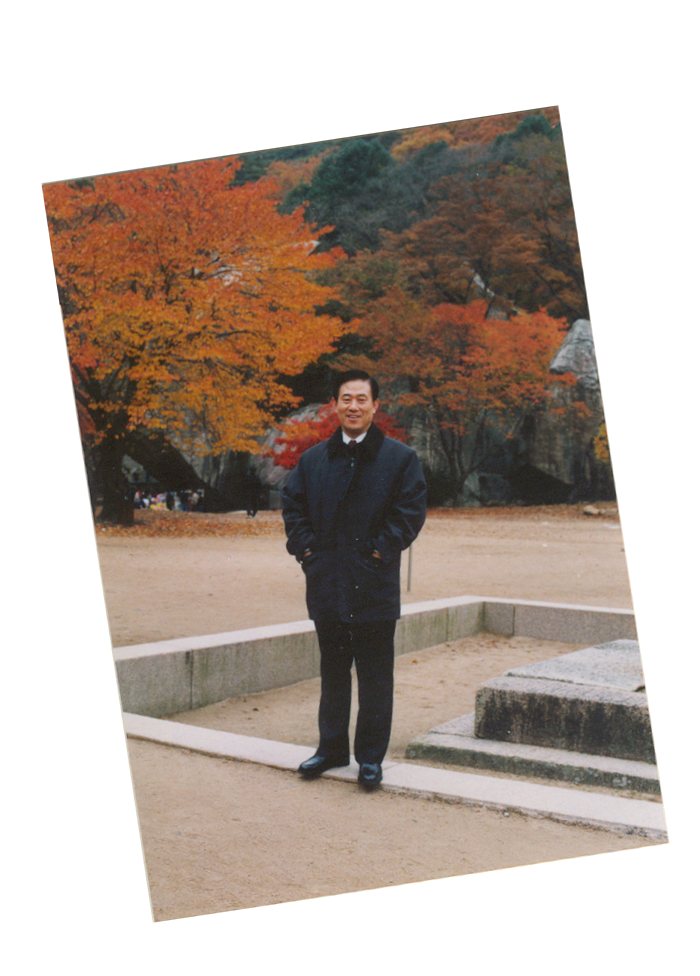
Ⅰ.ペテロとユダの対比と重生の必要性
ペテロとユダの物語は、ヨハネの福音書13章において劇的に対比されて描かれています。イエス様が弟子たちと最後の晩餐を共にされたとき、この二人は同じ席に着いていました。どちらもイエス様の弟子であり、ともに御言葉を聞き、奇跡を体験し、イエス様が注がれる愛の現場にとどまっていました。しかし決定的な瞬間に、二人の歩む道はまったく異なる方向へ向かいます。ペテロはイエス様を三度も否認する重大な罪を犯しましたが、最終的には悔い改めて戻ってきました。一方でユダは、イエス様を銀三十枚で売り渡した後、悔い改めることなく自ら命を絶ってしまったのです。同じ師に仕え、同じ真理を聞いていながら、一人は劇的な回復と恵みの道へ進み、もう一人は破滅の道を選んでしまいました。
この二人の人物像は、人間の弱さ、そして信仰の本質について多くの示唆を与えます。同じくイエス様の弟子であったのになぜこれほどまでに大きな差が生じたのか。ヨハネの福音書13章に登場する「足を洗う」出来事を通して、イエス様は「すでに体を洗った者は足だけ洗えばよい」とおっしゃいました。ここで「すでに体を洗った」というのは、根本的に罪の贖いを経験し、主の愛のうちに新しい命を得ている状態、すなわち「重生(新生)の体験」を象徴しています。ペテロはその後、三度もイエス様を否定するという大きな罪を犯しましたが、結局は尽きないイエス様の愛を思い起こし、悔い改めて戻ってきました。ところがユダは、その重生の体験がなかったため、罪を犯した後に与えられた回心の機会を逃し、最後まで自分を完全に主にゆだねることができず、絶望を選んだのです。
張ダビデ牧師は別の説教で「私たちの弱さはイエス様の十字架の愛のうちで根本的に変えられうる。しかしその愛の世界に入るためには、まず自分が罪人であると認め、真の重生を通して完全に新しく生まれ変わる必要がある」と強調しています。これはペテロが罪を犯した後にも戻ってこられた理由、そしてユダが長い間イエス様のそばにいながらもその愛を真に受け入れられず、ついには破滅の道を選んでしまった根本的な理由をよく示しています。重生とは、人間が罪の支配下にあった古い自分から解放され、ただ主の愛を信じて新しい命に生まれ変わる根本的な変化です。この体験があるならば、罪を犯したとしても最終的には主のもとへ戻り、回復の道を見いだすことができます。しかし重生を経験していないならば、罪の重みに押しつぶされ、自分自身を完全に壊してしまう危険もあるのです。
ヨハネの福音書3章に登場するニコデモの物語も、この点をはっきり示しています。ニコデモは指導者であり律法を知る人物でしたが、イエス様は彼に「人は新たに生まれなければ神の国を見ることができない」とおっしゃいました。水と御霊によって新たに生まれる体験、すなわち罪の本性から解放されて新たな人として生まれる実質的な変化がなければ、決して神の国を享受できないのです。これこそがペテロとユダの運命を分けた分岐点でもありました。イエス様が足を洗われたとき、ペテロは最初「決して私の足を洗わないでください」と理解できずに反発しました。しかしイエス様が「もし私があなたを洗わないなら、あなたは私と何の関係もない」とおっしゃると、ペテロはためらわずに「それなら足だけではなく、手も頭も洗ってください」と即座に応じました。この場面は、ペテロが結局は心の奥でイエス様の主権的な愛を受け入れる準備ができていたことを示しています。彼は決して完璧な人ではなく、その後、大きな罪を犯してしまいます。しかし「すでに体を洗った者」であったため、重生という土台の上で再び立ち上がることができたのです。
一方、ユダはイエス様の教えを頭で聞いていただけで、真の重生の体験がありませんでした。彼はイエス様を「メシア」としてではなく、自分の野望を実現する手段と考えていた可能性もありますし、あるいは政治的目的のためにイエス様の力を利用しようとしたのかもしれません。福音書に描かれるユダの行動を見れば、彼は経済的な欲や自己の正義感にとらわれていたように思えます。銀三十枚でイエス様を引き渡す際も、「主を裏切るのは絶対にしてはならない罪だ」という認識より、「これ以上の好機はないかもしれない」という打算が優先したのではないでしょうか。しかし事が起きてから現実が重くのしかかると、罪悪感に苛まれた彼は主の愛による悔い改めへと向かうことなく、自ら命を絶ちました。これこそ重生を経験しなかった者の悲劇的な結末と言えます。
張ダビデ牧師はまた別の説教で「真の信仰は、最終的には重生を通して主と人格的な関係を結ぶところから始まる。どれほど宗教活動に熱心であっても、礼拝に出席していても、多様な奉仕に没頭していても、本質的な生まれ変わりがなければ、状況が急変したときに簡単に崩れ去ってしまうのだ」と力説しています。実際、ペテロとユダは同じイエス様の弟子として多くの御言葉を聞きましたが、ユダは内面的変化を拒んだ状態でした。彼はイエス様に対する人格的な告白がきちんとなされないまま、自分自身が主となって生きていたのです。結局、彼自身が自我の重みと罪責感に押しつぶされ、完全に崩れてしまいました。
このように人間はみな弱い存在です。しかし重生によって、私たちは根本的な救いと赦しを体験できます。ペテロとユダの対比は「誰の罪が小さいか大きいか」を語ろうとするのではありません。二人とも深刻な裏切りの罪を犯しました。しかし一人はすでに生まれ変わり、主の驚くべき愛を知っていたために悔い改めることができたのに対し、もう一人はその愛を知らず、自らを見限ってしまったのです。ゆえにここで得るべき核心的な教訓は、「果たして私は主の愛と恵みを真に受け入れているか?」「私は本当に重生を経験したのか?」「だからこそ、つまずいたときにも再び戻れる信仰の根本が私の内に生きているか?」という問いです。
実際、重生は一度の感情的体験で終わらず、その後の人生の場において継続的に有効に働きます。重生した人でも罪を犯すことがあり、ペテロのように深刻な過ちを犯すかもしれません。しかし重生した者であれば、最終的には主の愛のうちに悔い改めて立ち上がる道が開かれます。ペテロは主の筆頭弟子と呼ばれるほどイエス様に近い存在でしたが、決定的な瞬間に「私はあの人を知らない」とイエス様を否定してしまいました。しかしその後、再び主のまなざしを受けて激しく泣き、主の愛を新たに悟ったのです。そしてその愛を握りしめて悔い改めることによって、使徒としての使命をまっとうしました。ユダはこの道を拒みました。同じ席にいたのに、生まれ変わらなかった自我のせいで戻ることができなかったのです。
私たちもこの物語を教訓として、自分自身を真剣に振り返らなければなりません。私は本当に重生を体験しているだろうか? 長年信仰生活をしてきたつもりでも、いまだにイエス様を利用して自分の野心や世俗的な目標を叶えようとしているだけではないか? 主の愛ではなく、自分の義や功績を頼みとしているために、もし罪に陥ったときに自分を受け入れられず、結局は絶望に陥る危険はないだろうか? こうした問いは、「すでに体を洗った者なのか、まだ洗っていない者なのか」を振り返らせます。重生がなければ、ユダのように罪の重みに捉われ、取り返しのつかない橋を渡ってしまいかねません。
結局、重生は単に「教会に通い、聖書を読む」ことだけではありません。それは十字架と復活の福音を真に信じ、キリストの愛のうちで古い自我が死に、新しい命に生まれる根本的な変化です。この変化を経た人は、世的な失敗や罪の泥沼に陥ったとしても、悔い改めの道が開かれており、主の強力な愛が再び彼を回復へと導きます。ペテロはこの真理を身をもって体験しました。私たちも同じ体験をすべきです。単に信仰知識が増えるだけではなく、心の奥深くで「主の愛が再び私を生かすことができる」という確信が必要です。その確信がなければ、私たちはユダと同じ選択をする危険から決して自由ではありません。
すでに主の愛によって体を洗ったのなら、これからは日々足を洗わねばなりません。人間は肉体の弱さゆえ、なお罪のほこりをまといながら生きる可能性があるからです。だからイエス様は「すでに体を洗った者でも足を洗う必要がある」とおっしゃるのです。これは日々自分を主の前に降ろし、悔い改めの生活をし、恵みを求めて新たにされていくことを意味します。ペテロのように失敗があったとしても、主の愛を思い出すなら、私たちはまた戻ることができます。しかしユダはこの道を拒みました。ユダはあまりにも大きな罪を犯し、その重みに耐えきれず、自殺という極端な道を選んでしまったのです。「生まれてこなかった方が彼のためによかった」(マタイ26:24)とイエス様が言われたように、彼が陥った絶望は永遠の闇だったのです。
したがって、ペテロとユダの対比を通して私たちは「必ず重生しなければならない」という切実な必要性を思い知らされます。もし今なお古い自我がそのまま生きていて、主の愛を真に受け入れられず重生の確信がないのであれば、何か決定的な瞬間が訪れたとき、私たちの選択はユダと変わらないかもしれません。教会での活動や信仰知識ではなく、十字架にかかり死からよみがえられたイエス・キリストの愛によって私の魂が根本から変えられる体験があってこそ、私たちは真に主の民となることができるのです。これこそヨハネの福音書3章と13章、そしてマタイの福音書26章など、さまざまな箇所が伝える核心的なメッセージです。張ダビデ牧師は多くの説教の中でこの核心を強調し、「一人の信仰的成功は重生の体験の上に立つが、重生が欠けた宗教活動は結局崩れ去るしかない」と説きます。これは現代を生きる私たちにとっても、深く適用される真理です。
Ⅱ.罪と悔い改め、そして愛の力
重生がなぜ必要なのかというもう一つの核心的な理由は、人間が罪を犯さざるをえない弱い存在だからです。ペテロもまた、イエス様への情熱が大きく、信仰告白も明確でしたが、決定的な場面でイエス様を否認してしまいました。ユダは愛のない自己中心的な信仰ゆえ、お金に目がくらんでイエス様を裏切りました。二人とも罪を犯したのです。それなのに、なぜペテロは悔い改め、ユダは悔い改められなかったのでしょうか。
悔い改めとは、罪を悟り、心を翻して再び主のもとへ戻る行為です。罪を犯さないことと同じか、あるいはそれ以上に重要なのは、「罪を犯したときにどう反応するか」という点です。重生した者であれば、主の愛を知っているので、罪の現場から立ち上がり「主よ、私は罪を犯しました。私を赦してください」という告白をもって戻ることができます。ペテロは主のまなざしの前で自分の罪を骨身に染みるほど悟りました。そして激しく泣きながら心を翻し、復活されたイエス様に出会って回復されました。
ユダは自分の罪を悟ったとき、主のもとへ戻ることをせず、自殺で人生を終わらせてしまいました。それはペテロより罪が重かったからではなく、主の愛を最後まで信じられなかったからです。張ダビデ牧師は別の説教で「罪を犯した者が神へ戻れなくする最大の罠は、サタンの告発である」と語っています。サタンは罪を犯した者に近づき、「お前は取り返しのつかない罪を犯した。主がお前を受け入れるはずがない」としつこくささやきます。この嘘を見分けられないと、人はユダのように絶望にとらわれ、自ら破滅を選ぶことがあり得るのです。しかし真の悔い改めは、このサタンの嘘を突き破って進む力です。主は「罪人であっても戻ってくることを待ち続ける。ルカ15章の放蕩息子のたとえのように、遠くからでも帰ってくる子をいつも見守り、走り寄って抱きしめられる」――これが福音です。
ペテロは苦しみの中で悔い改めましたが、その悔い改めには「主が私を変わらず愛してくださる」という信仰がありました。だからこそ、彼は罪を犯したにもかかわらず、その罪よりもはるかに大きい主の愛をつかむことができました。そして完全に新しい人となり、主の働きを担うことになったのです。ユダにはその道が見えず、最終的に絶望へ陥りました。ゆえに私たちは、悔い改めを軽く見てはなりません。罪を繰り返し犯すことも問題ですが、罪を犯しておきながら最後まで翻らなければ、真の破滅の道が開けてしまいます。
張ダビデ牧師は「悔い改めは単なる後悔や罪悪感にとどまるのではなく、罪から離れて今度は義へ向かう決断を意味する」と語ります。ただ「悪かったな、すまない」で終わるのではなく、人生の方向全体が変わるということです。これはイエス様が足を洗う場面でペテロが示した態度、そしてその後の人生にも反映されています。ペテロは主を否認した後、罪悪感に沈みましたが、復活されたイエス様に再び出会い、自分が主を三度否定したのと同じほど「主よ、私はあなたを愛します」と告白しました。主は「私の羊を飼いなさい」と彼に再び使命を託されたのです。過去の罪を乗り越え、新しい道へ踏み出す悔い改めがあったからこそ可能でした。
ですから重生を経験した者は、罪を犯すたびに再び十字架へ進む大胆さが与えられています。主の愛が自分を支えてくださるという信仰があるので、人間的な恥や恐れがあっても、また主のもとへ戻れるのです。これこそ「すでに体を洗った者は足を洗えばよい」というイエス様のお言葉につながります。根本的に重生を経験した人は「全身がきよめられている」状態です。しかし日常生活の中で罪のほこりが足に付いてしまう。そういうときには悔い改めによって足を洗うのです。これがペテロが示した生き方の原理といえます。ペテロも人生の中で多くの試行錯誤を経験しましたが、悔い改めて戻る道だけは決して放棄しなかったのです。
ユダと違ってペテロに「重生」という根本的転換点があったのは、主の栄光と愛を体験し、古い自分が死に、新しい命に生まれ変わったからこそでした。彼が罪を犯しても、最終的には回復への道へ進めたのは、罪よりも大きいイエス様の愛に支えられていたからです。旧約聖書でもダビデが大きな罪を犯した(バテシバとの事件など)にもかかわらず、心から悔い改めて神の赦しを受け、再び用いられたことが描かれています。人は誰しも罪を犯しうる存在ですが、その罪によって魂が永遠に破滅へ向かうか、あるいは悔い改めと赦しを通して再び生きるかは、私たち自身の選択にかかっています。そしてその選択を可能にする力は、主の愛への信頼と重生の体験にあります。
張ダビデ牧師はまた別の説教で「私たちは弱いがゆえに倒れることがある。しかし倒れたときこそ十字架の前にひざまずいて悔い改め、あの愛がどれほど大きく深いかをもう一度体験する。これが真の悔い改めであり、そこから再び主の人として生き始めることができる」と語っています。罪を犯さないことだけがすべてではありません。もちろん罪を犯さないように努力することはとても大事です。しかし人間は完全ではないので、罪を避けようと努めてもつまずくことがあります。そのとき、悔い改めて再び戻ることこそが何よりも重要なのです。結局、ペテロのように悔い改めて再び立ち上がり、神の人として生きることこそが祝福の道です。
イエス様は罪人を最後まで愛されます。イスカリオテのユダですら裏切る前まではイエス様の扱いを受け、晩餐の席に共にいました。イエス様は彼が悔い改めて戻ってくることを望まれたに違いありません。ペテロが裏切ったときにも、主は再び彼を抱きしめ、回復に導かれました。ヨハネの福音書21章でペテロに三度「あなたは私を愛しますか」と問いかけ、彼に再び弟子たちのリーダーとしての使命を委ねられたのです。これが主の愛です。罪を犯しても決して見捨てることなく、罪人が悔い改めるとき、新しく立ち上がらせてくださる――これが福音の力です。
ゆえに、罪を犯した後に最も重要なことは「悔い改めること」です。そしてその悔い改めを可能にするのは、罪よりもさらに大きく深い主の愛への信頼です。この事実を忘れなければ、どんな罪も悔い改められ、どんな挫折からも再び立ち上がれます。しかしこの愛を知らなければ、少し大きな罪悪感に押しつぶされただけで、ユダのように完全に崩れ去る危険があります。重生がなければ、悔い改めも困難です。なぜなら重生していない心は、いまだに自分が主の座についているため、「こんな大きな罪を犯したのに、本当に赦されるだろうか?」という疑いや自己嫌悪にとらわれ、ついには戻る道をあきらめてしまいがちだからです。
イエス様は「私は正しい人を招くためではなく、罪人を招くために来た」(マルコ2:17)とおっしゃいました。つまり、自分が罪人であるという自覚と、その罪を赦してくださる主の愛への信頼が相まってこそ、正しい悔い改めが実現します。これこそ教会の本質的なメッセージであり、張ダビデ牧師がさまざまな説教で繰り返し強調してきた点です。教会は罪人をただ裁く場所ではなく、罪を悔い改める者を受け入れ、新しいスタートを切らせる恵みの共同体であるべきだと教えています。その出発点は「罪から離れて主に立ち返る悔い改め」であり、その下地にはいつも「主の愛」が横たわっています。
ペテロが「すでに体を洗った者」であるということは、この愛を経験したということです。主が与えてくださる愛、すなわち十字架に示された赦しと救いの力を心底で体得していたからこそ、ペテロは根本的に新しい人となりました。しかしユダはその愛を真心から受け入れませんでした。彼には悔い改める機会が確かに与えられていたはずですが、主の赦しを信じるより自分の絶望を選んだのです。ここに私たちは「罪」「悔い改め」「愛」という大切な三角関係を見いだします。罪は人間に必然的に訪れうるが、悔い改めを通して再び義の道へ戻ることができ、その原動力となるのは主の愛なのです。この事実を知るならば、私たちは罪によって自分を見限ったり絶望したりせず、ペテロのように再び立ち上がることができます。
Ⅲ.死んで再び生きる、重生した人生の現実
重生と悔い改め、そして主の愛への信仰は、結局「死んで再び生きる体験」に要約されます。ペテロの悔い改めは、古い自我が砕かれ、新しい人として立ち上がる体験でした。ユダはこの死と復活の道を拒み、その結果、罪悪感に押しつぶされて自殺を選びました。死ななければ再び生きることはできない――これが福音の核心です。イエス様が十字架で死なれ、復活されたように、私たちも古い自我を十字架に付けなければ、新しい被造物として生まれることはできません。
使徒パウロはガラテヤ2章20節で「私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです」と告白しています。これは重生の本質を最も的確に説明する御言葉だと言えるでしょう。私が自分の人生の主人だった以前の状態は十字架で死に、今はキリストが私のうちに生きておられる存在になる――これが死んで再び生きる重生です。だからこそパウロはローマ8章で「ゆえに、今はキリスト・イエスにある者は決して罪に定められることがない」と宣言し、どんなものもキリストの愛から私たちを引き離すことはできないと確信するのです。重生はこの確信の源となります。ペテロもパウロも、そして初代教会のすべての聖徒たちがこの真理をつかんでいたので、世の迫害や苦難に揺らぐことなく福音を証しすることができました。
しかし死なしに復活はありません。イエス様はピリピ2章にあるように、「ご自分を無にしてしもべの姿をとり、へりくだって死にまで従順に従われた」からこそ、復活の栄光を得られたのです。同じように私たちも、古い自我を十字架につけて死ぬ過程がなければ、真の重生の復活を体験できません。張ダビデ牧師は「現代人は自分を完全に否定する過程を恐れ、十字架の道があまりにも辛いと感じて、簡単にあきらめてしまう。しかし真の信仰の道は苦難と死を通過してこそ命の喜びを味わうことができるのだ」とたびたび説かれています。これこそペテロが歩んだ道であり、すべての真のキリスト者が従うべき道なのです。
ペテロは最初「主のためなら牢に入るのも死ぬのもいとわない」と大言壮語しました。しかし実際にイエス様が捕らえられると、その恐れの前で「あの人を知らない」と否定してしまったのです。彼の古い自我がまだ死んでいなかったことを表す場面です。しかしその失敗の経験、そして復活された主との出会いを経て、ペテロは完全に打ち砕かれ、新しく生まれ変わりました。こうして使徒言行録においては、ペテロはイエスを伝えるために牢に入れられ、さらには殉教の危機に直面しても退かない、勇敢な証人へと変わったのです。古い自我は死に、いまやペテロの内にはキリストの命が生きていました。
ユダはまったく逆でした。イエス様を裏切った後、それがどれほど恐ろしい罪か悟りましたが、その重さに耐えきれず、古い自我が砕かれて新たに生まれ変わるよりも、自己中心的な絶望を選んでしまいました。死ぬべきは古い自我だったのに、ユダは存在全体を破滅させるほうに行ってしまったのです。このように重生を拒むならば、罪悪感と自己破壊のはざまで、行き場を失って崩壊するしかありません。
したがって、重生した人生とはイエス様が示された模範に倣い「自分を捨てて十字架を負う」生き方です。私たちは日常の中で大小さまざまな形の自己否定や自己犠牲を求められます。誰かを赦さなければならないとき、あるいは自分の思い通りにしたい欲望を下ろさなければならないとき、教会や周囲の人々を仕えるために時間や資源をささげなければならないとき、もし古い自我が生きているとすれば、その道を歩むのは困難です。「なぜ私が犠牲を払わなければいけないのか」「なぜ私があの人を赦さなければならないのか」という思いが湧いてきたら、十字架の道に従うことは難しいでしょう。しかし重生した人はすでに死んだ者として、キリストが自分の内に生きておられると信じます。ゆえに「主のためにこの道を行くのがふさわしい」と受け止めることができるのです。主の愛を体験した者は、その愛を与える道こそが命の道であると悟るのです。
また、重生した人生は「サタンの告発」に打ち勝つ力を与えます。サタンは「おまえが過去に犯した罪はどれほど重いか、そんなおまえがどうして主の愛を受けられるのか」とささやきます。あるいは「今の状況がこんなに苦しいのに、本当に神はおまえを顧みているのか」と疑いを吹き込みます。重生していない人はこの誘惑に打ち勝ちがたく、倒れやすいですが、すでに主の愛で体を洗っている人は「どんなものも私たちをキリストの愛から引き離すことはできない」(ローマ8:35以下)という真理を握りしめます。だからこそ、たとえつまずいても再び主のもとへ戻り、罪悪感や恥に押しつぶされて絶望することはありません。
張ダビデ牧師はある説教で「今日の教会の中にもペテロのような人がいれば、ユダのような人がいる。同じようにイエスを追っていても、ある人は重生して主の愛に根ざして生き、ある人は自分の打算や義を先に立て、結局主を離れてしまうかもしれない。大切なのは自分が本当に重生したか、そして重生した人生を実際に生きているかどうかだ」と語りました。この言葉は、現代の私たちにもそのまま当てはまります。教会に通い、奉仕をし、さまざまな活動をしていても、真の「死と復活の体験」がなければ、信仰は簡単に崩れる可能性があります。しかし重生した人は、苦難や逆境に遭遇しても最後まで主にすがりつくのです。
重生した人生は、自分の行いよりもはるかに偉大な主の恵みを信じる人生です。ユダは自分の行いや判断を優先し、その結果として崩れ去りました。彼は罪を主のもとへ持っていくよりも、自らの判断で自殺という結末を選んだのです。ペテロは大きな罪を犯したにもかかわらず、さらに大きな愛があることを信じていました。だからこそ再び主のもとへ戻り、最終的には初代教会を導く偉大な使徒へと成長しました。私たちの人生も同じです。私たちは誰もがユダと同じ弱さ、裏切りの可能性を秘める一方、ペテロと同じ悔い改めの可能性も持っています。その分かれ目は、重生によって「主の愛を本当に知っているか」、そして「私の古い自我は死に、キリストが私のうちに新たに生きておられるか」にかかっています。
イエス様はニコデモに「新たに生まれなければ神の国を見ることができない」と言われました。ここで「見る」とは単に目で見るというより、その国を現実に体験し、味わうことを指します。重生しなければ、神の国とその驚くべき栄光を決して知ることはできません。死と復活の体験を通らなかった人にとっては、十字架の道は愚かに見え、主の愛も空虚に聞こえるでしょう。しかし重生の恵みにあずかった人には、その道こそ真の命の道であると確信されるのです。だからどんな患難や試練があっても、この道を手放しません。
そして重生した人生は、教会の共同体の中でより豊かに顕れます。私たちが愛の真理を共に分かち合い、互いに受け入れ、仕え合う中で、日ごとに古い自我がさらに砕かれ、新しい人として成長していきます。教会とは、完璧な人々の集まりではなく、みなペテロのように罪を犯しうる弱さを抱えながらも、主の愛によって立ち上がり、重生を繰り返し確認し、広げていく共同体なのです。ユダが犯した罪そのものよりも、その罪を抱えて共同体の中に戻らなかったことこそが、真の悲劇でした。もし彼が罪悪感を主の前に下ろして戻ってきていれば、ペテロのように回復されたかもしれません。しかし彼は絶望に囚われて自己破壊を選び、その道はもはや引き返せない橋となってしまいました。
結局、私たちにもこのような選択の瞬間が訪れる可能性があります。日々の生活で大小さまざまな罪を犯し、ときには深刻な失敗を経験するかもしれません。そのとき「私はすでに主の恵みによって体を洗われた者だろうか?」と自問する必要があります。本当に重生しているのなら、どんなに大きな罪や失敗をしても、主のもとに戻る望みを捨てずにいられるはずです。なぜなら主が私の罪を十字架で負い、最後まで愛してくださると信じるからです。その信仰があれば、自分の罪を告白して悔い改め、再び新しい人生を始めることができます。しかし重生を経験していないならば、ユダのように罪の泥沼から抜け出せないと決めつけてしまい、絶望に陥ってしまうかもしれません。
張ダビデ牧師は「サタンは神の愛を疑わせ、罪人に『おまえはもう終わりだ』と絶えず落胆を吹き込み続ける。一方、聖霊は『たとえ罪を犯したとしても、帰ってきなさい。悔い改めれば再び生きることができる』と招く。教会の役割は、この霊的戦いにおいて罪人が主の赦しと愛をつかむよう助けることだ」と説きます。これはすべての信徒が実践すべき責任でもあります。私たち自身がまず重生を体験し、罪を見たときにはただ裁くだけでなく、その人が悔い改めて新しくされるように助け、愛をもって導かなければなりません。なぜなら主も私たちをそうして赦し、再び機会を与えてくださったからです。
最後に、死んで再び生きる重生した人生は、世に福音の力を証しします。ペテロは臆病者から勇敢な使徒へと変えられ、ユダヤ人たちの迫害を前にしてもイエス・キリストを宣べ伝えることをやめませんでした。この驚くべき変化は、人々の心を動かしました。同じように、私たちもかつては利己的で罪の中に生きていた者が、今は主の愛によって変えられ、愛の実や仕える姿勢を示すことで、世に福音を宣べ伝えることができます。「あの人はなぜあんなに変わったのだろう?」と人々が思うとき、私たちは「私の古い自我はキリストとともに死に、いまキリストが私のうちに生きておられるからだ」と証しできるのです。
結論として、ペテロとユダの対比は、重生の必要性、罪と悔い改め、そして死んで再び生きる重生した人生の現実を非常に明確に示しています。二人ともイエス様の弟子であり、二人とも罪を犯しました。しかしペテロは重生を通して主の愛を知っていたので悔い改めたのに対し、ユダはその愛を知らず、絶望へと突き進みました。これは現代を生きる私たちの信仰にもそのまま当てはまります。日々の生活の中で罪の誘惑は絶えずあり、いつか大きな試練に直面することもあるでしょう。そのとき、自分が「すでに体を洗った者」なのか、「主の愛を真に受け取り重生しているのか」が運命を分けるのです。重生した者は決して罪の中にとどまらず、悔い改めによって再び立ち上がり、最終的に主の御心に従って歩むことでしょう。
張ダビデ牧師は多くの説教を通して、「重生は一度きりの出来事であると同時に、その実を結ぶためには日々足を洗うように悔い改め、主の愛を新たに確認し続けることが必要だ。私たちはユダのように絶望せず、ペテロのように悔い改めながら生きなければならない。これこそ福音であり、これが教会の使命であり、重生した者たちの生き方なのだ」と強調してきました。結局、私たちの進む道は、イエス・キリストの十字架と復活へと続く道です。その道を歩むためには、古い自我が必ず死に、新しい命に生まれ変わらなければなりません。これが「生まれ変わり(重生)」であり、その実が愛と悔い改め、そして大胆な福音の証しとなって現れるのです。今日、私たちの人生にもペテロの悔い改めと愛の復活が再現されるよう願います。そして主の愛のうちにとどまる真の重生の歩み、死んで再び生きる復活の喜びが、私たち一人ひとりの人生に満ち溢れることを心から望みます。