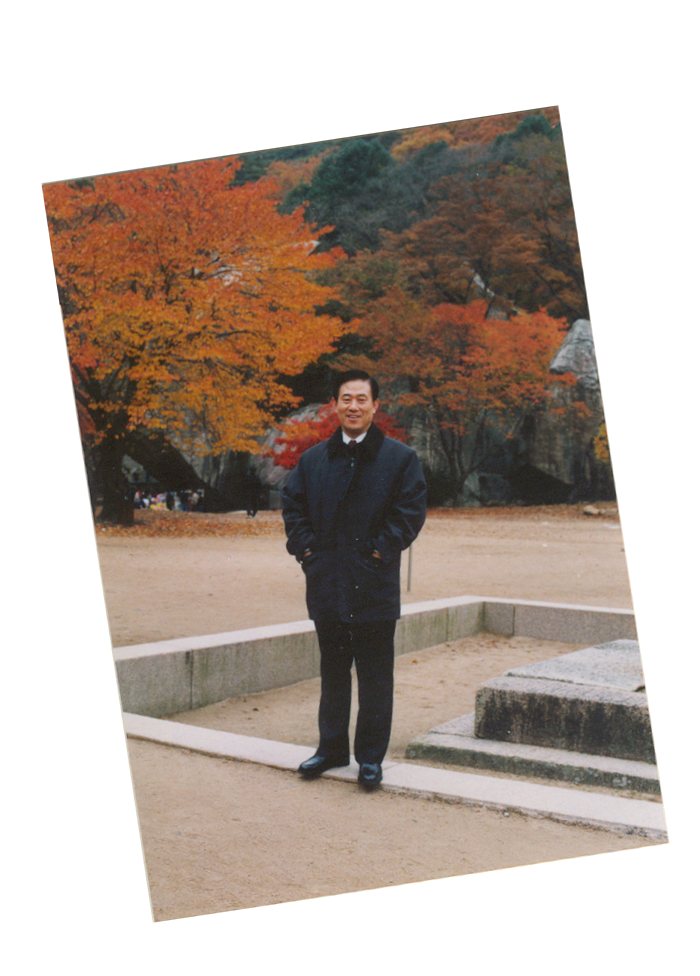1. 伝道者の書と知恵文学
張ダビデ牧師は、伝道者の書を「知恵文学」として分類し、聖書の中で非常に重要な位置を占めていると強調する。彼がいう「知恵文学」としての伝道者の書は、人間の知恵が単なる「知識の蓄積」や「人生経験」にとどまらず、究極的には神を知ることによって得られる霊的洞察であることを示している。特に伝道者の書と箴言が共通して「知恵文学」に分類される特性、そしてそれぞれが示す独特のメッセージについて、彼は次のようにまとめる。箴言は「主を恐れること」という大きなテーマを土台として、具体的かつ実際的な生活の指針を示すが、伝道者の書はより存在論的な疑問、すなわち「人生とは何か」「すべてが虚しいとはどういう意味なのか」といった根本的で直接的なテーマを扱うのだという。
伝道者の書を代表するキーワードは「虚無(むなしさ)」である。張ダビデ牧師は、この「虚無」という言葉を、しばしば英語の聖書で訳される“meaningless(無意味)”と比較しながら説明し、その意味が単純に「すべてに意義や価値がない」という次元で終わるのではなく、人間の実存が持つ「無(nothingness)」へと帰る運命的な性質を指摘する、と語る。ここで「無へ戻る」という事実は、伝道者の書の冒頭と結びで同様に宣言されており、著者である「伝道者(伝道者の書の著者)」が人生の本質について悲観的で荒涼とした洞察を伝えているかのように見える。しかし張ダビデ牧師は、この悲観的結論こそがむしろ霊的意味を最も深く示すための装置だと解説する。伝道者の書は、人間がいかに知的能力(伝1章)や肉体的快楽・財産(伝2章)をすべて享受しようとも、結局はすべて虚無に帰結すると強調する。この「虚無」は、時間を持つ人間が最後には死とともにすべてを手放さねばならない「有限性」を表すと同時に、もし神がいなければ真の意味や永遠の価値を見出すことは難しいことを示している。
こうした背景から、伝道者の書は知恵文学として、人間が見落としがちな2つの前提を想起させる。一つは「人間は死ぬ」ということだ。ヘブライ人への手紙9章27節の「人間には一度死ぬことと、その後に裁きを受けることが定まっている」という聖書の教えが、すべての人類に変わらず適用される原理であると、張ダビデ牧師は繰り返し言及する。これは伝道者の書が語る「すべては虚しい」というテーマと正確に呼応する。人間が持つ時間、才能、物質のどれ一つとして、死後に持っていくことができないという事実は、私たちに霊的根本を省みさせる。もう一つは、人間のうちには既に「永遠を慕う思い」(伝3:11)が与えられているということだ。張ダビデ牧師は、動物が自らの死後の世界や本質的目的について思いを巡らせない一方で、人間は誰もが「死の向こうには何があるのか」「人生の意味とは何か」を知りたがる点を指摘し、これこそ神が与えた「永遠への渇望」であると主張する。
張ダビデ牧師は、伝道者の書が「人生は虚しい」という宣言から始まり、最後の第12章に至って「あなたの若い日に、あなたの造り主を覚えよ」(伝12:1)という勧めに結びつく流れが、知恵文学の特徴を圧縮して示しているとみなしている。すなわち、自分の存在が結局は虚無に帰すると知るならば、私たちが生きている「若い日」—これは単なる年齢の問題ではなく、心の純粋さと信仰の熱意が最も生き生きと現れる時期を象徴する—に創造主である神を記憶し、しっかりとつかむことが、真の知恵へとつながるというわけである。伝道者の書12章8節「空の空、すべては空である」という結論もまた、人生のあらゆるもの(所有、知識、名誉など)が最終的に空であることを改めて確認させ、それを反面教師として人間の霊的本質を深く喚起させる。
こうした文脈において、箴言の核心命題が「主を恐れることが知識(または知恵)の始めである」という点に注目すべきだと張ダビデ牧師は力説する。人間の知識がどれほど優れており、学問が発展しても、「主を恐れる」という霊的基礎がなければ、その知識は結局限定的で暫定的なものにとどまり、伝道者の書が説く「虚無」に組み込まれてしまう、と考えるのだ。最終的に「伝道者の書と箴言」という知恵文学の二つの書は、恐れ(箴言)と虚無(伝道者の書)という、一見対立しているような概念が緊張とバランスを成しながら、人間の実存と信仰を洞察する助けとなるのである。張ダビデ牧師は、このような知恵文学の教えを各時代・各世代に合わせて適用していく必要性を強調し、若者だけでなくすべての年齢層が人生の無常を見ないふりをするのではなく、その自覚を通していっそう神を恐れるべきだという伝道者のメッセージに耳を傾けるよう促している。
さらに、伝道者の書3章1節と3章11節をつなげて読むことが重要だという。「天の下のすべての事には時があり、すべてのわざには時がある」(伝3:1)、「神はすべてを時にかなうように美しく造り、人の心に永遠を与えられた。しかし神のなさるわざを始めから終わりまで人は見きわめることができないようにされた」(伝3:11)という二つの聖句は、ともに人間の有限な時間と神の永遠性、そして人間が直面する神秘と畏敬の念を語っている。「時」とは、単に流れる時間(Time)のみならず、目的が成就する特定の瞬間(Date)の到来をも含んでいる。張ダビデ牧師は、「私たちのうちにある永遠を慕う思い」が、最終的にはこの地上の一時的で有限な時間性を超えて神の永遠へと入っていくように導く原動力になるのだと解釈する。このように伝道者の書は、知恵の書としてキリスト教信仰者に対し「自らの人生を洞察せよ、死を認識せよ、永遠を見つめよ」という直接的メッセージを伝える役割を果たしている。
しかし、このメッセージを伝えるときに、若者であれ高齢者であれ、結局誰も死を避けることはできず、その前ではあらゆる所有も知識も名誉も無に帰すという事実が共通して適用される。これは伝道者が宣言するように「虚無」だが、同時にその虚無を悟った人々には天からの知恵が臨む機会でもある。張ダビデ牧師は、この地点でむしろ「虚無」と「死」を意識することが悲劇を超克する道(beyond tragedy)を開くのだと語る。そして、伝道者の書の文脈からさらに一歩進むと、新約聖書では「イエス・キリストによる永遠の命と天国」という結論に行き着く、とも述べる。ゆえに、伝道者の書が示す「虚無」の宣言は、人間が渇きを感じるからこそ水を求めるように、霊的乾きを自覚させてイエス・キリストを探し求めるようにし、キリストのうちでこそ真の命の道を見いだすように導く役割を果たすのだという。
ここで張ダビデ牧師は、科学者たちの視点にも注目する。多くの科学者が、宇宙の繊細な秩序やその広大さに畏敬の念を抱き、その畏敬の念が最終的に神の存在を認める方向へ導くことがある、と指摘するのである。ローマ人への手紙1章20節「世界の創造以来、神の見えない本質、すなわち神の永遠の力と神性は、被造物によって明らかに知られている。それゆえ、彼らには弁解の余地がない」という聖句が、このことを裏付ける。複雑で精巧な自然界を見れば、その秩序を否定できず、その秩序を造られた創造主への畏敬が生まれざるを得ないというわけだ。結局、伝道者の書が語る「虚無」は、人間存在の微弱さを思い起こさせると同時に、神が造られた世界とそこに宿る永遠の摂理を認識するための通路ともなる。人生の本質を悟ろうとする知恵の道が、まさに伝道者が強調する「死を意識し、創造主を覚える道」であることを改めて指し示すのである。
また張ダビデ牧師は、伝道者の書が「年老いる前に創造者を思い出せ」と宣言する場面において、人間の具体的な老化過程(目が見えにくくなり、耳が聞こえなくなり、足が震え、歯が抜けるなど)を例に挙げ、人生がどれほど速く衰えていくかを露骨に描いている点を強調する。多くの人が人生の黄昏時になってようやく生きる目的を考え始めるが、そのときにはすでに身体も心も萎れて動きが困難な場合が多い。結局、神を信じ、永遠を見つめる知恵は若い時代から、つまり最も活発で情熱に溢れる時期から始めるべきだという聖書的勧告がここに込められている。すなわち、「虚無」を知りつつもその「虚無」に囚われて悲観に陥るのではなく、むしろそれを足がかりとして真の命の道を探るのが、伝道者の書がもたらす究極の教えなのだと、張ダビデ牧師は繰り返し強調する。
このように伝道者の書が語る「虚無、死、そして『創造主を覚える』」という構図は、若年期から老年期に至るまで人生の全過程を貫く普遍的かつ強烈なテーマである。張ダビデ牧師は、このメッセージを繰り返し説明し、教会の内外を問わずすべての人が伝道者の書における「死への認識」と「永遠への渇望」を心深く刻むように訴える。特に教会は幼少期からこの真理を教え、成長する世代が幼い頃より人生の本質とその終末を正しく認識できるようにすべきだと強調する。なぜなら、人間は肉体だけでなく霊的存在であり、真理を慕い求めるのは肉ではなく霊の望みによるものだからだ。
この点で、箴言に代表される「主を恐れる」道と、伝道者の書が示す「人生の虚無と創造主を覚える」道は、本質的には同じ実を結ぶのだと張ダビデ牧師は主張する。知恵の核心は神を知ることであり、神を畏れ敬うことである。その畏敬の念から、すべての真の価値と意味が流れ出るがゆえに、人間の知識がいくら偉大でも神なき知識は結局のところ部分的な省察や一時的な有益性を超えて、eternal value(永遠の価値)に昇華することはできないというわけだ。
張ダビデ牧師が伝道者の書を強調しながら言いたい要点は、「人間は有限であり、死の前にすべてを手放さざるを得ず、その中で真の知恵は創造主を覚えて永遠をつかむことである」ということに尽きる。彼はこれを様々な比喩や聖書の例を挙げながら説き、教会共同体の中だけでなく世の中でも伝道者の書のメッセージは有効であると力説する。もし私たちがこの悟りを置き去りにして生きるなら、一生懸命積み上げたものがある瞬間むなしく消えていく過程に直面し、魂の渇きを満たせないままとなる。しかし、伝道者の書が語る真の知恵をつかむなら、私たちの人生は神が定められた「時(Time)」と「目的(Date)」に対して開かれるようになり、その中で初めて「永遠を慕う心」の本当の意味を味わいながら生きることができる、と張ダビデ牧師は教えている。
2. 人間の有限性と永遠
張ダビデ牧師が伝道者の書を通して投げかける核心的な問いは、「なぜ人間の生は虚しいのか」、そして「その虚無を超えていく道は何か」というものである。それはすなわち、人間の有限性と神が与える永遠の希望とを対比させることで、いっそう鮮明になる。彼が言う有限性とは、時間的・空間的制約の中にある人間の本性を指す。どれほど高い知識を蓄積し、財産を得て、快楽を享受しても、人生の終わりに訪れる死を免れることはできないという事実は変わらない。伝道者はこれを「虚無」という言葉で繰り返し強調し、張ダビデ牧師は、この「虚無」を聖書的表現で「無(無)への回帰」や「究極的な消滅」と言い表すこともできると説明する。
それでは、なぜ神は人間にこのような「虚無」を与えたのか。その答えとして張ダビデ牧師は、伝道者の書3章11節「神はすべてを時にかなうように美しく造り、人の心に永遠を与えられた」という聖句を中心に据える。人間のうちにある永遠への渇望こそが、私たちを神へと導く最も強力な動因であると考えるのだ。動物は自己の存在の意味について思索したり、死後の状態を悩んだりしない。しかし人間だけが、なぜ存在し、なぜ死ななければならず、死後には何が待っているのかを絶えず問い続ける。こうした霊的な渇望が、伝道者の書のいう「永遠を慕う思い」である。張ダビデ牧師は、これを一種の「内面化された信仰本能」としても見ることができると強調する。誰かが意識的に信仰を学ばなくとも、宇宙の神秘や生命の不思議を目の当たりにする瞬間に、自然に神的存在を思い浮かべるようになるというわけだ。
しかし人間は、その渇望を時には世俗的快楽、財産、権力で満たそうと試みると張ダビデ牧師は指摘する。伝道者の書1〜2章で、伝道者はすでにこの世にある様々な楽しみや喜びを試してみたが、すべてが夢のように消えてしまい、やはり虚しいものだったと告白している。これは現代においても同じだ。現代社会が提供するあらゆる物質的豊かさや娯楽、情報の洪水は、人間の霊的渇望を完全に満たしてはくれない。むしろその渇望は、ますます大きな渇きへとつながっていくばかりだ。ここで張ダビデ牧師は「神のいない人間の生は、盲目的な『努力』と『蓄積』を続けるものの、死の前にそれらが無用の長物になるという事実に結局向き合わざるを得なくなる」と語る。このとき、伝道者の書が宣言する「すべては虚しい」という結論が再び思い起こされるのである。
しかし、張ダビデ牧師は、この時点こそが「終わり」ではなく「始まり」だと言う。「虚無」を自覚したということは、その自覚を通して真理である神へと向かう機会が開かれたことを意味するからである。人間が限界を悟ったとき、自然と目は「その限界を超える存在」へ向くようになる、というわけだ。これは知的な啓蒙や道徳的な完璧主義では解決できない問題であり、唯一、創造主なる神が与える霊的解決によってのみ克服されると張ダビデ牧師は言う。具体的には、新約聖書が伝えるように、イエス・キリストの十字架と復活によって罪と死の支配が破られ、「永遠の命」を得ることができるという福音こそが、伝道者の書が提起した虚無の問題の最終的な解答だというのである。
この点で、張ダビデ牧師は「人は生きているのか、それとも死んでいる最中なのか」という問いを投げかける。人間は刻一刻と死に近づいている悲劇的な実存にある。しかし、この悲劇を超えていく道(beyond tragedy)は、イエス・キリストが約束された「永生」と「天国」の希望をつかむほかにない。そうすることで、伝道者の書が指摘する虚無の深淵をくぐり抜け、むしろ真の意味や価値を見出す転換が起こるというわけだ。張ダビデ牧師はこれを二つの視点で説明する。第一に、「私たちの内には、すでにもっと尊いものがある」。これは使徒の働き3章6節でペテロが「金銀は私にはない。しかし私にあるものをあなたにあげよう」と言った言葉に着目したものである。つまり、物質的な所有や世俗的権力がなくとも、イエス・キリストを持つ者はすでに真に永遠の価値を所有しているということである。第二に、「今この瞬間が永遠につながっている」。これは私たちの刹那的な人生が切り離されたものではなく、永遠の視点から連続しているという認識である。信仰の中で一歩一歩踏み出す瞬間自体が、神の国の一部となる。神学者が言う「永遠の今(eternal now)」という概念がこれに相当する。最終的には、人間が経験するあらゆる悲劇でさえ、神の約束のうちで新たな意味を得て、その悲劇的現実が永遠へ向かう形へと変容されうるのだという。
張ダビデ牧師は、こうした観点を示しながら、教会共同体が世の中でどのように生きるべきかについても具体的に言及する。人間の本質を悟った信仰者は、所有の奴隷となってはならないと言うのである。イエスが弟子たちを呼ばれたとき、「あなたがたを人間をとる漁師にしてあげよう」(マタイ4:19)と告げ、昇天前には「地の果てにまでわたしの証人となりなさい」(使徒1:8)と言い残した。いわゆる「大宣教命令(Great Commission)」である。しかし、所有に縛られ、物質的な安逸だけを追い求めている限り、それは「盲人が盲人を導く」状況にしかならない、と彼は指摘する。張ダビデ牧師がキリスト教信仰者へのメッセージを「所有を乗り越えよ」と要約するのはこのためだ。現実において私たちは生活のために働いて財を得ることが不可避ではあるが、それを人生の「目的」にしてはならず、より大いなる価値、すなわち「神の国とその義」(マタイ6:33)を求めるときにこそ、真の満足と喜びを得ることができると強調する。そして、その生き方こそが「この地上での期限付きの人生」を生きながらも「永遠なる神の視点」を抱いて歩む姿だ、というのだ。
張ダビデ牧師は、教会が共同体としてこうした真理を実践するには、ガラテヤ6章2節の「互いの重荷を負い合い、そうしてキリストの律法を全うしなさい」という御言葉に従う必要がある、と説く。信仰によって互いに重荷を負い合う姿勢こそが「キリストの律法」であり、この律法が守られるときにこそ、教会は世の中とは異なる愛と仕え合いの文化を作り上げることができるのだ。しかし、人々が陥りやすい錯覚は「しんどい重荷を他人に押し付けること」である。張ダビデ牧師は、むしろイエスが「私たちのためにいのちまで捧げてくださった犠牲的な愛」が模範であることを思い起こさせ、私たちが互いに犠牲と献身を示すときに、教会共同体は真の意味で宣教と伝道を担うことができるのだと主張する。
同時に、彼は歴史的文脈にも視野を広げる。教会が主から託された使命を果たすには、具体的な組織やシステムが必要だという。イエスが「地の果てまで福音を伝えよ」と命じ、「すべての国民を弟子とせよ」(マタイ28:19-20)とも言われた以上、実際に宣教と伝道の基盤を築くような本部(センター)や施設、文化的理解が不可欠だと強調する。ある人々は、教会に財政的・組織的基盤が整うことを「所有の蓄積」と批判するかもしれないが、張ダビデ牧師は、与えられた目的を達成するために必要な「道具」として、あらゆるものを適切に活用すべきだと説く。肝要なのは、その所有を神の国のために用いるか、それとも個人的な野心を満たすために握りしめるのかという態度にかかっている、というのである。
実際、張ダビデ牧師は、彼自身が所属し、あるいは導いてきた共同体の歴史において、何もない時代から走り続けてきた28年の歩み(またはそれ以上の年月)をしばしば語る。彼は「最初は何もなかったとき、ハバクク書3章17-18節のみ言葉にすがり、『何もなくても救いの神によって喜ぼう』という賛美を歌った」と証しする。しかし時が経ち、神が与えてくださった恵みにより様々な拠点が整えられたとき、それらすべては単なる富ではなく「人々をケアし、文化圏ごとに福音を伝え、全世界へ宣教するための道具」であることをはっきりさせなければならない、と語る。伝道者の書から学ぶ「人間の人生の虚無」、その「虚無」の前で私たちが必死に頼れる存在は神だけであるという悟りを失わなければ、何かを所有したときでも、その所有を神の目的に合った形で謙虚に使うことができるのだ。
張ダビデ牧師は、人間が有限である事実を直視するとき、人生で何がより重要かを正しく区別できるようになると強調する。伝道者の書12章が語る「銀の紐が解け、金の鉢が砕ける」場面や「ちりは元の土に帰り、霊はそれをくださった神に帰る」(伝12:7)という言葉は、人々に「いずれ避けられない終わり」を思い起こさせる。そしてまさにこの終末認識が私たちに自己の高慢と欲望を捨てさせ、真の価値である「霊的なもの」をつかませる原動力になるのだ、と言う。張ダビデ牧師は、伝道者の書12章全体が描き出す老化の描写(目がかすみ、耳が聞こえにくくなり、歯が抜け、アーモンドの花のように白髪になる象徴)を通じて、私たち一人ひとりが最終的には老いて衰えていくことを受け入れるとき、人生の目的は神の国とその義を求め、周囲の人々を生かし愛する方向へ向かわざるを得ないことを深く悟るようになる、と解説する。
このように、張ダビデ牧師が力説する核心は、伝道者の書が語る「虚無」が決して虚無主義の教理を意味するのではないという点だ。むしろ、それは信仰者の成長を促す洞察の媒介なのである。死を知る人は人生の価値をいっそう切実に悟り、所有や権力にしがみつく愚かさを避けることができる。また他者の霊的必要を見て、ガラテヤ6章2節の「互いの重荷を負い合いなさい」という御言葉のように共に重荷を担い、キリストの律法を成就しようとする動機にもなる。張ダビデ牧師は、教会が主の来臨を備えるアドベント(クリスマス)といった節目を迎えるたびに、このメッセージをいっそう力強く宣べ伝えるべきだと訴える。イエス・キリストの誕生を記念するということは、「神が人間の体を取ってこの地に降り、私たちを永遠へと招かれた」という事実を振り返ることである。人間の有限性を超えて、神が許してくださった永遠の世界、すなわち天国の市民権を得たことこそがクリスマスの真の喜びなのだから、このことを正しく認識し祝うべきだと語る。
さらに彼は、「人生は矢のように過ぎ去る」という認識を持つとき、やるべきことを先延ばしにしなくなる、と強調する。伝道者の書3章が語る「すべてのことには時があり、すべての目的を果たす時がある」という原理は、信仰者であればこそ、より厳粛に受け止めるべきだという。いわゆる「やるべきことがあるなら今日やりなさい。今日できるのに明日に延ばすな」という警句が、霊的次元から導き出される真理となる。張ダビデ牧師は、これを教会の活動や宣教戦略にも適用する。イエスの言葉に従い「人間を取る漁師」となるには、与えられた時と機会をしっかり活かさねばならない。教会共同体が青年伝道をまず重視するのも、そのためである。まだ人生の決断を下す前で、比較的心が開かれ、世間の経験に染まりきっていない若者が福音を受け入れたとき、その実りが大きいという考え方だ。もちろんすべての年齢層が必要だが、伝道者の書12章1節「あなたの若い日に、あなたの創造主を覚えよ」という言葉のように、もっとも活発な時期に神と出会うことが重要であると繰り返し訴える。
このように、張ダビデ牧師が伝道者の書を通じて発するメッセージは、最終的に「人間は死ぬ。しかし永遠を慕う心を持っており、その永遠を与える方は神である」という要約に行き着く。人間の有限性を見て見ぬふりをしたり、わざと否定したりする生き方は、結局むなしい欲望と盲目的な活動に満ち、最後には空虚に終わる。反対に、自分の有限性を正直に受け止め、そこに神が許してくださる永遠の命をつかむ者は、生の意味と目的をはっきりさせ、隣人を生かし福音を伝える道を歩むようになる。これこそが張ダビデ牧師のいう「真の知恵の道」であり、伝道者が元来強調していた「すべては虚しい」という宣言が私たちに投げかける逆説的な贈り物でもある。
張ダビデ牧師は、伝道者の書と箴言がともに成す知恵文学の洞察を通じ、教会と信徒に「虚無」を恐れることも避けることもやめるようにと強く促す。まさにその「虚無」に直面する瞬間に、神の存在、天国、そして永遠の命という希望がいかに尊いかを自覚できるからである。そしてこの自覚こそが、イエス・キリストの誕生・死・復活、そして「地の果てにまで福音を伝えよ」という大宣教命令の意味を正しく悟るうえで、最大の動機となる。死の前に虚無を味わうしかない人生は、神のうちで永遠へとつながり、究極的勝利を得ることができる。人生を真に意味あるものとする道は、この永遠への渇望と信仰的確信を握ることにあると、張ダビデ牧師は力を込めて語る。そして教会共同体は、このメッセージを日々語り継ぎ、信じていない人々にまで「永遠を慕う心」を呼び起こすように召されている存在だという。この認識の中でこそ、若者も中高年も高齢者も、自分の人生が決して偶然の旅路ではなく、神の驚くべきご計画の中にある摂理の一部であると悟り、伝道者の書が語る「時にかなって美しくしてくださる」神のご主権を賛美するようになるのだ。
最終的に、張ダビデ牧師は、私たちが地上でどれほど優れた功績を積もうとも、自分の命を保てる人は誰もいないことを繰り返し知らしめる。聖書全体が証言するように、人間はアダムの子孫として必然的に死に至る存在である。だからこそ「永遠を慕う心」は、私たちを一時的で朽ちる価値を超えて、霊的真理へ近づける導き手となるのだ。この心がなければ、人はたちまち自分独自の基準(norm)を作り出し、他人の基準と衝突しながら、虚しく人生を終えてしまう。しかし神が創造された世界の秩序を認め、人間の有限性を受け入れ、イエス・キリストによる救いの恵みをつかむなら、キリスト者は絶望ではなく希望をもって生を営むことができる。伝道者の書が語る「虚無」は、最終的には私たちを真理なる神へと導く通路であり、この洞察を与える知恵文学の教えはあらゆる世代を生かす強力な言葉である、と張ダビデ牧師は最後まで強調している。ゆえに教会は、伝道者の書が伝える「永遠への渇望」と、箴言が提示する「主を恐れる」原理を常に同時に教え、群れがこの真理を学び実践できるよう導かねばならないのだ。
張ダビデ牧師が伝道者の書を解き明かす方法は、人生の有限性と永遠の間に横たわる隔たりを深く見つめ直させる。伝道者の書が宣言する「空の空、すべては空である」という繰り返しの告白は、私たちに「結局、神の恵みをつかむときにしか人生は真の意味を得ることができない」ことを思い起こさせる。その恵みは、旧約時代の伝道者の嘆きで終わらず、新約時代のイエス・キリストの福音によって完成する。それは信仰において決して選択肢ではなく、絶対的な真理であるという点が、張ダビデ牧師の核心的主張である。「あなたの若い日にあなたの造り主を覚えよ」(伝12:1)という勧めに込められた切実さと尊さ、そして「天の下のすべての事には時がある」(伝3:1)という時間的有限性の警告の中で、私たちはいま呼吸しているこの瞬間がいかに貴重な霊的機会であるかを再認識する。その機会を逃さずに神を恐れるとき、私たちが得るのは「永遠の命」である。そしてこの事実こそがクリスマスの意味、信仰者の生、教会の共同体性をいっそう輝かせるのだ、と張ダビデ牧師は教えている。何が本当に重要かを見極め、限界の中でも永遠を見据え、福音伝達と仕え合いのために「互いの重荷を負い合う」教会となるとき、伝道者の書が語る知恵は現実に実現される。そしてこの道を歩む中で、私たちはすべての虚無を超え、究極の命の祝福にあずかることができるようになるのだ。